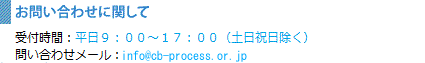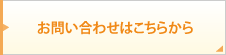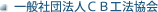施工編
- タケ節鉄筋・ネジ節鉄筋は継ぐことはできますか?
- タケ節鉄筋とネジ節鉄筋は同じ鉄筋のJIS規格です。
JIS規格同士なので、継げます。
- 一日の施工数を教えてください。
- 200箇所程度/(一班・日)施工できます。
- 電気の準備はどうすればいいですか?
- 溶接機1機当たり、三相200V85Aの分電盤が必要です。
または、溶接機1機当たり、45KVAの発電機が必要です。
- 製造会社が異なる鉄筋は継ぐことはできますか?
- 鉄筋はJIS規格があるので、どの製造会社でもJIS規格になります。
JIS規格同士なので、継げます。
- 管理方法を教えてください。
- 外観検査+引張破壊検査 or 外観検査+超音波探傷試験を行ってください。
- 降雨・降雪・暴風時は施工できますか?
- 原則できません。
施工を行う場合は、監理技術者・管理技術者と協議してください。
- 使用できる鋼種と鋼径を教えてください。
- SD235・SD295・SD345・SD390・SD490が使用できます。D13~D51まで使用できます。
SRもSDと同じ取り扱いをしてください。
- 異径鉄筋は継ぐことはできますか?
- 継げます。
- 異鋼種は継ぐことはできますか?
- 継げます。
- 施工前試験は実施するのですか?
- 管理技術者様の判断によって、実施する場合と実施しない場合があります。
実施する場合は、最大径・最大鋼種の3本を検査するのが一般的です。
外観検査+引張破壊検査 or 外観検査+超音波探傷試験を行ってください。
曲げ試験は必要ありません。鉄筋が90°曲がると建物は倒壊しています。