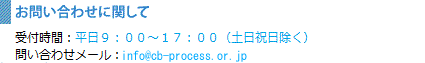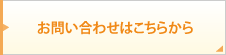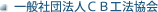一般編
- CB工法はどれくらい施工されているのですか?
- 建築・土木含め年間340万箇所の施工実績があります。(2023年1月1日現在)
- 溶接継手の分類・種類を教えてください
- 溶接継手は、シールド方式、裏当て材の種類で分かれます。
シールド方式は、治具シールド方式とトーチシールド方式があります。
トーチシールド方式が一般的で、CB工法はトーチシールド方式です。
裏当て材は、セラミックス製、銅板製、鋼板製があります。
CB工法は溶接作業後に裏当て材を取り外せるセラミックス製です。
- 継手の種類を教えてください。
- 建設省告示第1463号では、圧接、溶接継手、機械式継手に分類されます。
- 見積や施工の相談はどこに問い合わせをすればいいですか?
- 全国、北海道から沖縄まで95社の施工会社様がいます。(2023年1月1日現在)
弊社のHPに各施工会社様の連絡先が掲載されていますので、ご確認ください。
- NETISに登録していますか?
- NETISには登録していました。
(旧)KT-990020
- CB工法の特徴を教えてください。
- 溶接作業後に裏当て材を取り外せることが出来るため、全周外観検査ができます。
施工スピードが速く、一箇所あたりの溶接時間は、D35で60秒程度です。
溶接部が大きくならないため、鉄筋と同じかぶり厚さで検討できます。
溶接作業時に鉄筋を引張ったり、回すことがないので、施工性に優れています。
- 海外での施工は可能ですか?
- ベトナムや台湾で施工実績があります。詳しくは、弊会にお問合せください。
- 鉄筋継手とはなんですか?
- 鉄筋と鉄筋を継いで、鉄筋を長く加工します。
日本では道路の関係上、鉄筋は12m程度の長さまでしか運搬できません。
(都内では、6m程度の長さしか運搬できません。)
長さ12mの鉄筋では、建物を造ることが出来ないため、現場で継手を行います。
- CB工法で施工するには、(公社)日本鉄筋継手協会が発行する資格書は必要ですか?
- (一社)CB工法協会と(公社)日本鉄筋継手協会は別団体の為、CB工法協会が発行している溶接技量適格性証明書(CB工法溶接技術資格証)があれば施工は可能です。